1エンジニアとして高校の共通必修科目「情報I」の教科書を読んでみた
2024/09/03

masyus
2022年度から高等学校で共通必修科目になった「情報I」ですが、1エンジニアとして
- 今後情報Iを習得して社会人になった人が、どのような基本スキルを備えてくるのか気になった
- これから先、どのような基本スキルを備えた社会人と仕事することになりうるのか知っておきたい
と思うようになりました。そのため今回「情報I」の教科書を1冊手に取ってみて読んでみましたので、概要と感想を記事に書き起こします。
購入した本: 数研出版 「高等高校 情報I」
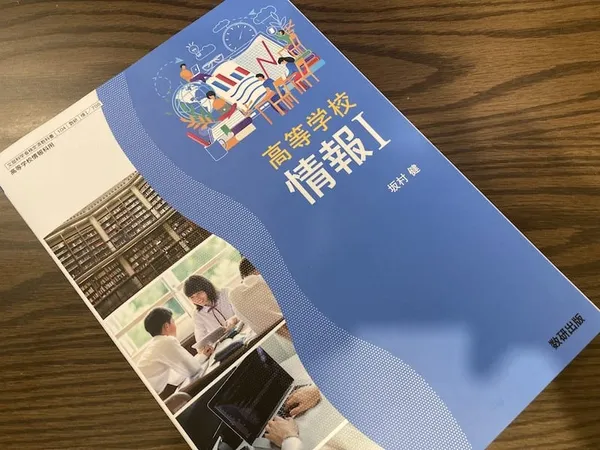
実際に買ってみたのは数研出版の「高等高校 情報I」という教科書です。文部科学省検定済教科書なので、実際に高校で使われている本であろうと推察されます。中身はテキストと図や絵などがバランスよく含まれているため、可読性が良いです。
「高等高校 情報I 」の概要
目次を辿りながら紹介します。
- 第1編 情報社会の問題解決
- 第1章 情報とメディア
- 第2章 情報社会における法とセキュリティ
- 第3章 情報技術が社会に及ぼす影響
- 第2章 コミュニケーションと情報デザイン
- 第1章 情報のデジタル表現
- 第2章 コミュニケーション手段の発展と特徴
- 第3章 情報デザイン
- 第4章 プレゼンテーション
- 第3編 コンピュータとプログラミング
- 第1章 コンピュータの仕組み
- 第2章 プログラミング
- 第3章 モデル化とシミュレーション
- 第4編 情報通信ネットワークとデータの活用
- 第1章 ネットワークのしくみ
- 第2章 データベース
- 第3章 データの分析
エンジニア目線で見るとなかなか面白い内容も入っています。プログラミングだけでなく、ネットワークやデータベースにも触れるんですね。各編のサマリーは下記です。
第1編 情報社会の問題解決
- 情報とは何なのか?情報の検証や信頼度、問題解決のためのPDCA活用
- 個人情報や知的財産権、著作権、情報セキュリティ
- 情報技術の発展に伴い普及してきたSNSやAIについて、SNSを活用した情報発信時の注意点
第2章 コミュニケーションと情報デザイン
- ビットや16進法、文字コードのデジタル表現、画像や動画の形式と圧縮
- コンピュータとスマートフォンの変遷、出版や放送などのマスコミュニケーションの変遷、グラフを活用した情報の表現方法、ユーザーインターフェース
- プレゼン方法
第3編 コンピュータとプログラミング
- ハードウェアとソフトウェア、浮動小数点と誤差
- 二分法探索などのアルゴリズム、プログラミング言語
- シミュレーションのためのモデル化、待ち行列、モンテカルロ法
第4編 情報通信ネットワークとデータの活用
- インターネット、通信プロトコル、パケット通信、IPアドレスとドメイン名、DNS、WWW、HTML、暗号化
- データベースの概要、トランザクション、POS
- CSVなどのデータ形式、一次・二次データの収集方法、分散と標準偏差、形態素解析
個人的な見解
概説からも分かるように、本教科書は「情報」について浅く広く解説していました。内容的にはITパスポート試験ほどではないですが、
世の中の「情報」における基礎を押さえている
と感じました。
「情報Iの内容だけでエンジニアになれるか?」かと問われましたら「たぶん無理」だと思いますが、少なくとも押さえるべき基礎は知れる本になっているというのが所感です。逆に言えば、今社会人として仕事されている方は
情報Iの内容を背景知識的に把握していないと、今後仕事に支障をきたす
可能性はあります。
また、これは率直な感想ですが
情報Iの授業を受けてから社会に出る方々は恵まれている
と思いました。私が高校生だった時代、記憶が曖昧ですが情報という授業自体があっただろうか。。確か数学の教科書の一番後ろにそれっぽい内容はありましたが、授業でもスキップされがちでしたし、大学の試験範囲にもあまりなっていなかったような気がします。
今回読んだ本のリンク紹介
本教科書に興味を持たれた方は実際に買って読んでみてください。教科書ですのでお手頃な値段で購入できるかと思われます。私は単純に読んでて楽しかったです。
余談
- 2025年1月の共通テストから「情報I」が加わるらしいです。7教科21科目。昔は5教科7科目だったような、、
- 独立行政法人 大学入試センターが作成している「情報I」の試作問題がありました。今度試しに解いてみたいと思います
- 今回たまたま興味本位で高校の教科書を取り上げましたが、中学校の「技術・家庭」における技術分野の教科書も改めて読みたくなりました(別途購入してレビュー記事書きます)
